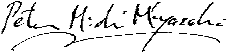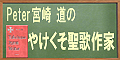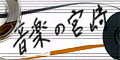初出: 「古今聖歌集改訂試用版」(2001)
リズムのトリック
2001年の「改訂古今聖歌集試用版」でお披露目されてから、日本聖公会では新しい聖婚式聖歌として広く認知されている聖歌です。古本純一郎主教+我が父・宮崎尚志のコンビによる聖歌はもう一つ、第295番「あいするものの死をいたみ」がありますが、どちらもシンプル且つ非常に優れた骨格を持つ、完成度の高い聖歌です。
教会の友人がある一時期、立て続けに結婚したこともあって、頻繁にこの聖歌「むかし主イエスは」を歌う機会に恵まれ、私自身の聖婚式でも歌いました。しかし意外とこの聖歌は、ひねりが利いていて難しい。5〜6小節間に、拍子がひっくり返ったか?果て又変拍子か?と思わせるような箇所があり、ブレスの間を如何に、どのように取るかで悩む、奏楽者泣かせの1曲でもあります。歌う方も、このトリックのような箇所でバラバラになることしきり。
しかし、何故そうなるのかを注意深く楽曲解析すると、5〜6小節間のフレーズに、一種の“リズムのトリック”が仕掛けられているためです。

5小節目からサブドミナントのBbのコード(和声)になりますが、この和音が6小節目の1拍目いっぱいまで保続されています。詞を考慮に入れず、曲だけで考えた場合、6小節目は1拍目からトニックのFに戻った方が良いと、普通は考えます。
しかし、この“仕掛け”は、決して悪戯に用意されたものではありません。結論から言いますとこの聖歌は、曲の隅々に渡って歌詞のセンテンスに合わせて旋律がフレーズ化されて作曲されており、譜面上ではキチンとした混声合唱の聖歌譜面(我々はよく“串団子”と呼ぶ形)になっているものの、旋律及び和声は“1-2-3-4”と拍子を数えて歌うことを強く拒絶しています。それは歌詞に則した“フレーズ”で歌うことを求めているためです。
とはいえ、“1-2-3-4”と拍子を数えないと歌えないんですぅ〜・・・、とおっしゃるなら、6小節目の1拍目のバス声部“Bb”を、“F”にすると問題解決に近づけるでしょう。小節目のアタマで、主調へのコード・チェンジ(トニックへの解決)が行われることによって、小節単位での全ての調和が満遍なく取れます。
但し、その場合1節目の「水をぶどう酒(しゅ)にかえ・・・」の「酒」にアクセントを置かずに歌うことが望ましい。「しゅ」が「主」などと聞き違うことを回避する事は必至となり、歌い方というものに気を付けないと、こども達にとって恰好のからかいのネタになります?!
子供の時分、旧祈祷書(文語)のニケヤ信教を「主イエス渡さるる夜、パンをとり、謝してのちこれを割き、弟子に与えて言いたまいけるは、取りて食せよ。」のような箇所で「言いたマイケルは・・・フォー!」とか言って笑っていたものです・・・どうでもいい話ですね。しかし子供心ってそんなもんです。
逆に、譜面通りに歌うと、さほど気にせずとも「水をぶどう酒に」までが(小節線をまたいでまで)同じ和音で通していますから、聞き違うような歌い方自体が難しいのです。実は譜面通りに何も考えずに歌うだけで、この聖歌は言語と音楽が互いにサポートしあう最良の瞬間に出会う事が出来るのは、紛れもない事実です。
文節の区切りの処理
続く「愛する二人を祝したもう」への間が他に比べて短いのは、前の「水をぶどう酒にかえ」との文節的な繋がりによるものです。
むかし主イエスはガリラ色ヤのカナにて水をぶどう酒にかえ
//
愛する二人を祝したもう
(ミラクルを見せて結婚祝いをした…みたいな)
・・・ではなくて、
むかし主イエスはガリラヤのカナにて
//
水をぶどう酒にかえ 愛する二人を祝したもう
(結婚祝いのためにメークミラクル…みたいな)
・・・であります。当然、文節の区切り方で、歌が描くシチュエーションは大きく変わります。主イエスは「ガリラヤで水をぶどう酒にかえた」のが重要なのではなく、「ガリラヤで結婚式を挙げている男女を祝した」ことが最大のポイントなワケで、水をぶどう酒にかえたのは飽くまで「愛する二人を祝す」ために行った、ささやかな行為です。聖書に於いても、イエスの行なった奇跡は、敢えてそれに接した人に口外しないでくれと口止めをするほど密やかなものであり、こうした奇跡がキリスト教の根幹を支えるものではありません。
問題の「水をぶどう酒にかえ」と「愛する二人を・・・」の短い間に、ブレス・タイムをキチンと取って次のフレーズに会衆を正しく導くため、総じて奏楽者が大きく間を空けています。文節の区切りはブレスの“間”で付けられるものであります。ここでの間の取り方が他の文節と比べて大きくなるほど、リズムのトリックが転じて、難解な変拍子になっていくと同時に、歌われている内容も本来とは違ったニュアンスで人々に届くことになるのです。
ニュートラル
しかし実際に何度か歌ったことがある多くの人々にとっては、譜面通りに歌ったり、演奏したりする事の方が、反対に困難になるでしょう。この聖歌が非常に覚えやすい節回しを持っているキャッチーな曲であることが、却って最初に歌った時の印象、即ち「第一印象」を強烈に脳に刷り込んでしまうためだと考えられます。この印象が強ければ、後に変えることは何より難しい。つまり「なんかヘン」な曲のまま、この聖歌ならではの急速に得られる「慣れ」のもたらす錯覚によって、結果として脳はそれを「心地よい」と解釈するに至る。
その結果、実は聖歌が持つ莫大なポテンシャルを損なってしまう事に、誰も気付かないまま「そういうモンでしょう」で止まってしまうのです。これは立体の多面体に等しい「音楽」というものを、1つの平面のみで捉えたに過ぎず、極めて大きな損失であることは幾重にも強調すべきでしょう。第457番「主にしたがいゆくは」の実態が行進曲(マーチ)であることは誰の目にも(耳にも)明かでしょうが、私のバンド“Elpis”がやっているように、節回しを全く変えずに譜面通りに歌うバックにテクノ・ハウスの躍動するビートを置くだけで、曲はダンサブルなディスコ・サウンドに変わったりするものです。踊れます! しかし印象がガラリと変わって、音楽が最初から持っている新たな側面を垣間見せるというのは、単に曲そのものが持つ多面体的なキャラクター、又はポテンシャルを一部分だけ引き出したに過ぎないことも、また真実です。
総じて音楽は、出来る限りニュートラルな姿勢で聞いたり歌ったりすることによって、様々なものが見え、聞こえてくるものです。時には敢えて、反作用的に何かをぶつけて、意識的にニュートラルにしなければならない事もあり、この聖歌に関しては現在、そうしたほうが良いと思います。
実はこの聖歌、ドラムスにリズムを叩かせてみると実に美しいバラードになり、宮崎尚志らしいポップ&キャッチーなフィーリングが一気に炸裂します。リズムのトリックの部分も、一定のリズムさえあれば抜群に理解しやすい。なんだ、実はこういうことだったのか、というナチュラルなフィーリングが掴めます。実例(下のリンク)を聞いてみて下さい。この録音はテンポが74ぐらいで、かなりゆったりしています。聖歌集では勿論記載されていませんが、作曲者のオリジナル譜ではテンポ指定が83です。
「むかし主イエスは」- Band Remix
(歌:ミネストローネ)
聖歌のフレキシビリティーについて
聖歌の譜面は、ダイナミクスやテンポなどの細かい演奏指示は省かれています。即ちそれは、作曲者の意志が楽曲を支配するのではなく、礼拝を行う人々が、それぞれの礼拝環境に則した解釈をし、そして行うだけの余地を非常に大きく取ってあるという意味なのだと思います。故に、聖歌のほとんどがシンプルな譜面であり、それらは「楽曲の基本」に等しい。そこに何を足そうが(10,000人のオーケストラで奏楽したって良い)、どんな楽器で奏楽しようが(オルガンであろうがアカペラのコーラスであろうが)、果て又、4リズム(dr,b,g,key)のバンドで演奏しようが、一向に構わないのです。それだけフレキシブルに展開できる余地があり、又、それを行ってはいけない等とは、どこにも定義されておりません。
即ちそれは、聖歌を演奏する事に「定型がない」ことを表しています。その分、普通の音楽にはない、膨大なフレキシビリティーが提供されるのです。それは、演奏したり奏楽したり歌ったりする我々が同様にフレキシブルでなければ、とても享受出来ないほど。
そのフレキシビリティーとは、聖歌が持つ様々な「表情」だと考えると捉えやすいでしょう。例えばリズムを入れただけで活き活きと表情を変えるものもあります。そして教会生活を送っている我々は、そうした聖歌の新たな表情に接した時・・・たったそれだけの些細な事なのに・・・大きな喜びを見出すものです。それは、聖歌が多様性に耐えうるシッカリとした骨組みの上に成り立っている事の証であると同時に、音楽の歓びを身近に示してくれる素晴らしいものだという事です。
そこに「定型」を作り、はめ込んで定着させようとする行為は本来、やらんでもえぇ〜こと。聖歌の持つ多才な表情を1つにすることは、音楽の歓びを半減させ、ニュートラルな姿勢で居ることも難しくさせてしまいます。私はこの聖歌「むかし主イエスはガリラヤの」は、早々に定型が出来つつある聖歌の代表例であると思います。